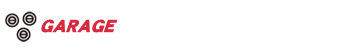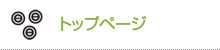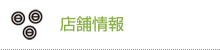2024年締めにあたり・・・トライシクルでエンジンを組むという事。
今年もいよいよ残すところ僅かとなりました。
最近よく「ブログ楽しみにしています」という身に余るお言葉を頂きます。
毎回、好き勝手に言いたい事を書いてる私にとって本当に有難い事です・・・
あまりこういった事は公表はしたくはないのですが、トライシクルでエンジンのオーバーホールをして頂いている方に報告も兼ねての内容です。
このブログでも口が酸っぱくなるほど言い続けている「部品がない!」というワードですが、本当に嫌になるほど補給品は皆無です。
せっかくエンジンを開け、各部計測をし、要交換部品を発見しても新品補給品はないので、「中古良品」を使うか、「見なかった事」にするしかありません・・・
特にヤフ〇ク等の「中古良品」ほどタチの悪い物はなく、何度もエッらい目にあわされてきました・・・

これはクランクの右先端部ですが、殆どの車両はこの先端のオイルシールと接触する部部が腐食や擦りキズがあり、これで本当に一時圧縮が保たれるのか不思議です・・・
材質が弱いのか、オイルシールのリップの当たる部位はツメで引っかかる程の傷がある事が殆どです。

折角、ベアリングやセンターシールを交換して入念に芯出しをしても、こんな状態のカラーで組みたくはありません・・・
よくお客様からラビリンスシールにした方がいいか?とか、雑誌に掲載された記事を見てその様な加工ができないかと問い合わせが多くありますが、そらやらんよりやった方が絶対ええに決まってます、が、しかしである!この辺りの所をちゃんとやった上でせんとそれこそ本末転倒です・・・
センターシールだけ半永久的に使えてもサイドシールはゴムのままやし、サイドシールの方が断然弱いのにどないやねん?と首をかしげたくなります・・・
エンジン加工に湯水の如くコストをかけられる方は稀で、やはり優先順位を間違えてはいけません。
一点豪華主義ではエンジンの調子は絶対にでません・・・やはり補器類も含めたトータルで考えないと意味がないんです。
何台も他のお店で「フルOH」をしたというエンジンも開けましたが、この箇所がちゃんとしたクランクを見た事がありません・・・
新品部品は出ないので、おそらく前出の「見なかった事」にしているんだと思います・・・

ただ、幸いにもこの部分は取り外し可能なので、汎用旋盤で比較的簡単に制作する事ができます。
中にはバラせる事を知らずにそのまま見て見ぬふりをして組んでいるショプさんも多いですね。
鍛造品であるクランクの素材との相性などはメーカーの開発さんレベルでないと判りませんが、
自分の知識で出来る限りの素材を吟味して製作しているつもりです。
何よりキズまみれのそれより絶対いいハズ!と信じて製作しています。

これはクラッチのプシュロッドシールとプッシュロッド短ですが、ココも殆どの車両がシールとの接触面が爪で引っ掛かるほどのダメージを受けています。これも比較的簡単に制作可能ですが、常に力のかかる部分なので大事を取ってSKD11という素材で制作しています。

嫁と畳は新しい方がええ。って昔のエラい方は言ってますが(笑)新品に勝るものはありません。
この様な部品は組んでしまうと外からは見えません・・・
見えなくなってしまうからこそちゃんとしておきたいと思っています。何年か後、ウチで組んだエンジンを誰かが開けた時、その人間がどう思うかを常に考えてエンジンを組んでいます。
雑誌で取り上げられる様な華やかな物でもありませんが、優先順位を間違わない様、常に自問自答しながら日々悩む毎日です。

これは今後製作予定?のトリプルの鬼門、チェンジシャフトロッドです。
例によってここもオイルシールとの接触面が摩耗し、M/Tオイルが漏れます・・・
ここからオイル漏れをしていないトリプルは本当に稀で、ガレージにオムツは必須です。
やはりこの頃はまだイギリス様式の「右チェンジ」の考えが抜けきれず、シフタードラムが右側にあるマッハ系全ての泣き所で、W1SAよろしく長いチェンジシャフトで、むりくり左チェンジにしていたんでしょうね・・・実際、H1には右側にもシャフトが出ていますから。
右から長いシャフトで繋げている構造上、絶対に回転方向以外の力がかかり、ただでさえキズまみれの接触面に縦方向の力も加わりオイルが漏れます(涙)
Z辺りから北米を意識してか、最初から左チェンジありきで設計されているので、「新世代」のエンジンといえます。
Zどころか下手するとFXと同世代のKHですらマッハの時代のままの一世代も二世代も前の設計で、本当にダメですね。
このすぐブリブリになるチェンジシャフトは絶対に新たに作りたいのですが、先端のチェンジリンクが付く部分は転造と言ういわゆる「ハンコ」のようなもので制作するんですが、転造は大量生産には向ていますが、金型を新たに作る必要があり、少量生産には向きません・・・
なんとかスプラインを切る工場様で制作できる見込みは経ちましたが、コストの問題で頓挫しています・・・
当時物のレプリカなら少々高くても売れるんでしょうが、こんな見えない部分にいったい何人の方が買ってくれうのだろうか?と毎度の「棚の肥やし」理論で未だ制作には至りません・・・今の所、私も見て見ぬふりをするしかないのが現状で、本当にはがゆい思いをしています。

これらの部品は基本、非売品です。この他にも無い物は多数ワンオフで製作しできる限り交換する様にしています。
せっかく数あるショップの中からウチを選んで頂いたお客様に「専門店」の値打ちもないとダメですもんね・・・
ウチは基本トリプルしかやりません。っていうとカッコよく聞こえますが、実はトリプルしかできないんですよね・・・
有難い事にたまにフォーワンとかの依頼もありますが、丁重にお断りしています。何故なら専門でないので知らない事がいっぱいあるからなんです。
一部例外を除き、何んでもできるショップって結局の所、何んでもできないと思うからなんです・・・
トライシクルでエンジンを組む。という事ですが、まだまだ自分自身で納得がいくエンジンには程遠いです。
ただ、一つ気がかりなのは、非売品でない物でさえ殆どのショップ様が「業販して欲しい」との要望がありません・・・
私はお客様の為になるなら、他店様にあってウチには無い部品は躊躇せず業販して頂ています。
だけどウチの部品も本当に一部のショップ様しか買って頂いていないのが、儲けとかではなくトリプルを愛す身からすると本当に寂しいですね・・・
早く「フルオーバーホール」という言葉が使えるようになりたいと日々願う毎日です。
皆様、どうぞ良いお年を!
KH250 400用 クロームメッキスポークセット

KH250 400 SS400 S2T用 クロームメッキスポーク&ニップル前後1台分セット、高品質な日本製です。
前後1台分セット 80本 定価30800円(税込み)
製造は大手オートバイメーカにも納入実績のある国内工場にて生産しておりますので、安心してご使用頂けます。
当初、やはりサビの問題から、40系ステンレスにて制作予定でしたが、乗り心地や、「折れ」の問題もあり、 スチールに「クロームメッキ」を施す事で、通常のユニクロ&クロメートメッキ仕上げに比べ、各段の耐久性と、対候性を持たせる事ができました。
クロームメッキも国内工場にて施工致しておりますので、海外製のチープなテカテカな輝きではなく、シットリとした艶に仕上がっております。
尚、どうしてもニップルに純正の様な色付が欲しい方は、クロメートメッキ仕上げのニップル仕様も別途ご用意しております。
お気軽にお問合せ下さいませ。

泣き所
トリプルシリーズに乗る限り、避けて通れないのが「ギア抜け」です。
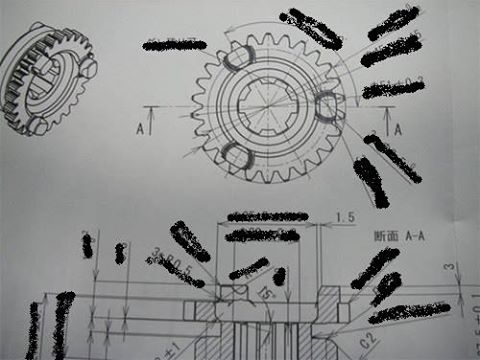
非力なKH250ですら、ミッショントラブルが発生するのに、その倍以上のH1やH2なら・・・(汗)
カワサキトリプルシリーズは長兄のH2から、末弟のKH250まで基本的な構造は変わりません。
H2に限っては殆どH1とミッション強度が変わらないので、マッハらしい走りをすると、確実にミッションが逝ってしまいます。
クラッチの切れが悪いのもありますが、当時はSCM21と言う一応クロームモリブデン鋼で制作されていますが、焼き入れなど、当時は浸炭焼き入れなどが主流で、現在のSCM435+高周波焼き入れなどを施したギアとは雲泥の差があります。
どうしても、ドックが摩耗するとギアのかみ合わせが悪く、より抜け易くなり、さらに摩耗するという負のスパイラルに陥ります・・・
もちろん新品純正部品など、とうの昔に欠品となっており、中古のギアをだましだまし使うしかありませんでした。
「無いなら造るしかない!」
とはいえ、Z系みたく数を読める訳でもなく、中型でマイナーなKHのギアを制作しても売れるとは・・・
でもあきらめきれません!!
とりあえず量産するかどうかは別として、一番消耗が激しいセカンド(フォースギア)の試作品を作る事にしました。
もちろん粘りも強度も段違いのSCM435材に高周波焼き入れ+ショットピーニング(WPC処理)で完璧に仕上げ、自分のKHで長期テストをしてみたいと思います。
明けましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願い致します。
今日はシーズカンパニーの登山さんの所へ新年のご挨拶によったら、
ナント、元カワサキ&モリワキファクトリーライダーだった多田選手がいらっしゃいました。

物凄くフレンドリーな方で、終始緊張ぎみの私に気さくに声をかけて下さったり、当時の濃~い裏話などを聞かせて頂け、本当に夢のような時間でした。
あの黄金の80年代を駆け抜けたカワサキの侍にお会いできた上、
ナント私のKHにまたがってくれて記念撮影。


それはもう家宝にさせて頂きます!
多田さんの現在の愛車がGPz750Rだったのが侍らしく、凄く印象的でした・・・
多田さん、登山さん本当にありがとうございました。